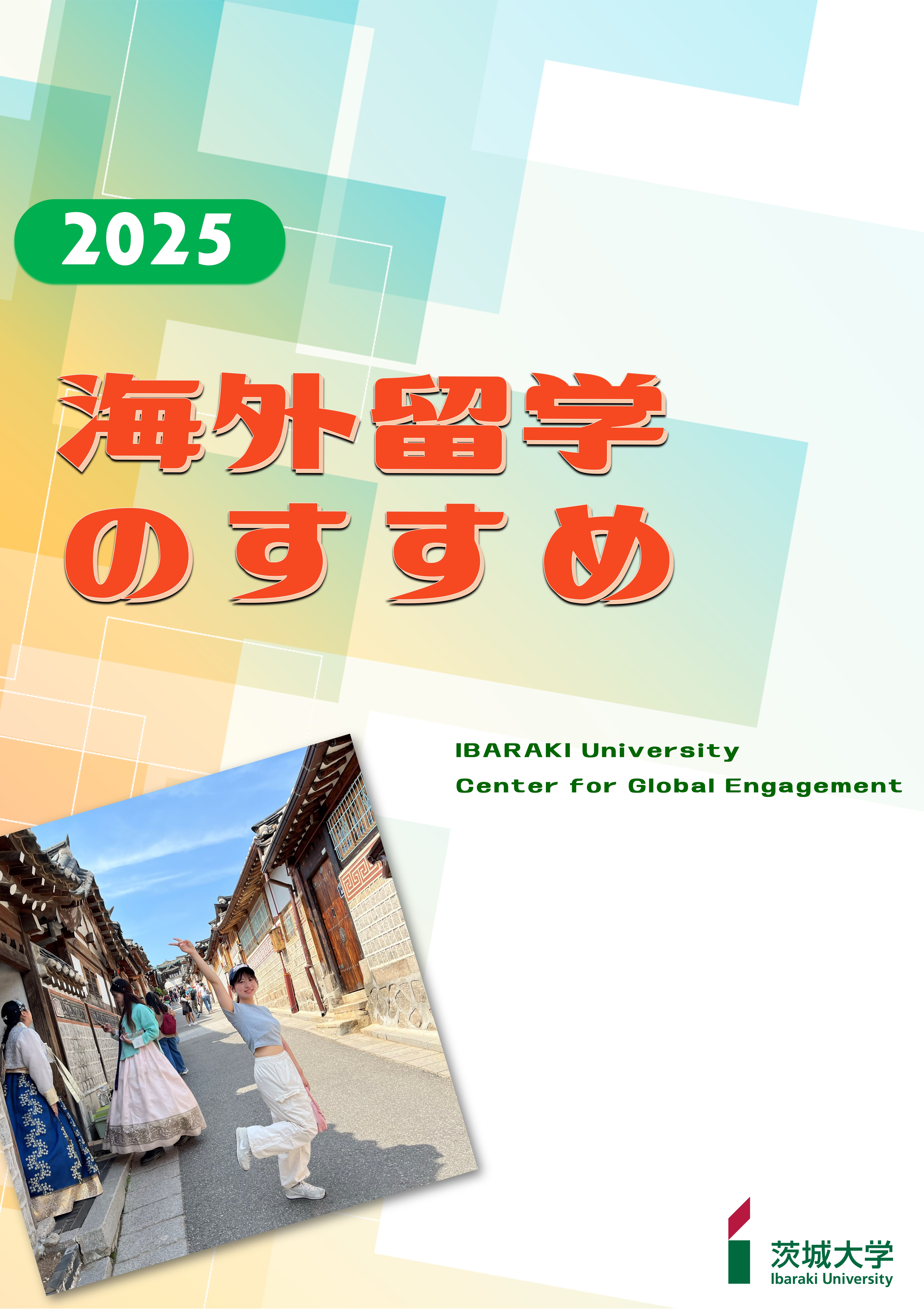海外留学を希望するみなさんへ
Introduction of Global Education Center
留学体験・協定校情報
現地語で開いた心の扉

農学部
留学期間2024年度研修 AIMS派遣プログラム
授業で学んだ専門的な内容について
UGMで履修した科目は “Traditional Fermented Food of Indonesia”、“Plant Morphology and Systematics”、”Fishery Biology”、”Seed Technology”の4科目である。その内の“Plant Morphology and Systematics”と”Seed Technology”の2科目はPracticum(実習)クラスが含まれ、講義以外に実験や課外活動を含むPracticumの活動時間があった。これら4つの科目の中で特に印象的な科目は、“Traditional Fermented Food of Indonesia”と“Plant Morphology and Systematics”である。“Traditional Fermented Food of Indonesia”では、基本的にはインドネシアの発酵食品についての講義が行われ、講義内で学んだ発酵食品やその関連発酵食品についてのプレゼンテーションとディスカッションが行われた。授業内容はとても興味深いもので、初めてインドネシアの伝統的な発酵食品の材料や製造工程について学んだにもかかわらず、私たち留学生の出身国の発酵食品と比較しながら解説されたため理解しやすかった。
“Plant Morphology and Systematics”はPracticumとセットの科目であり、実践的に学習できる科目である。講義とは別のPracticumでは、大学内の植物を中心に主に熱帯地域で見られる植物をマテリアルとして時には実際に学内でそれらのマテリアルを見周りながら学び、自分のノートにスケッチや情報をまとめることで植物の形態や系統分類を学ぶことが出来た。
海外の大学で授業を履修するにあたって工夫した点および反省点
現地のUGM(ガジャマダ大学)ではできるだけ普段の大学の講義で学んだことのない分野や科目を中心に学ぶことを意識した。茨城大学では主に食品科学とその派生科目について学んできた。食品分野以外を学ぶという意味で、”Fishery Biology”や”Seed Technology”、”Plant Morphology and Systematics”の3つを学んだ。また、食品科学の分野の中でも今まで学んだことのないインドネシアの発酵食品という分野について学びたいと考え、”Traditional Fermented Food of Indonesia”を受講した。どの科目も学んだことのない知識や内容ばかりで有意義な科目であったと感じている。ただし、その中でも”Seed Technology”、”Plant Morphology and Systematics”のようなPracticum(実験や課外活動)を伴う科目が存在し、それらの内容をあまり知らない状態で履修を組むのはリスクがあると思う。Practicum科目は、科目によって活動内容や日程、課される課題内容、そのハードさがかなり異なるため、それらについて何も知らないまま授業をとると想定よりも課題が多くて苦しむ事や逆に想定よりも活動内容が少ないなどのギャップを感じることがあり、それはリスクがあると考える。そのため、履修を組む前に、特にPracticum科目について知り合いや先生方にその内容やハードさを必ず尋ねるべきである。
多様な文化・価値観に触れることで得られたこと
インドネシアの国民の約85%がイスラム教徒という事もあり、UGMで知り合った生徒らの大半がイスラム教徒(ムスリム)だった。留学以前は現地でムスリムの方と友達になれるかとても不安があり、あまり心を開いてくれないのでないかという先入観をもっていた。しかし現地に行ってみると会う人達皆友好的で、積極的に話しかけてくれたため安心した。
現地ではインドネシア語学習に積極的にトライし、主に”Duolingo”等の携帯のアプリでインドネシア語の単語やフレーズをインプットして、現地の学生とそれらを使って会話してアウトプットするという形で学習していった。現地の言語で現地の方々に話しかけると、皆笑顔で明るく返事をしてくれ、自分の言葉が伝わるととても学んで良かったという気持ちになった。さらに現地の言葉で話しかけると心を開いてくれてスムーズに会話が進んだ。この経験から敬意をもって現地語で話す事の大切さを見出すことが出来た。
留学で得た知識・経験を,自身の将来にどのように活かしていくか
留学中に身につけた能力として質問する力と適応力が挙げられる。例えば留学中の衣食住で困った事や分からない点を現地の友達やバディ、滞在先のオーナーさんなどに尋ねる事で少しずつ現地の暮らしに適応する事が出来た。また、現地語であるインドネシア語を積極的に学び、現地の人々とインドネシア語で会話する事で現地の生活にいち早く慣れようと努力した。このように留学中の日常生活の中で分からない事を尋ねる力と新しい物事への適応力を培う事が出来た。これらの力を今後の研究活動や就職活動の際に積極的に尋ねて情報収集を行う場面で活かす事ができると考えている。また、適応力は大学院に進学した時や就職した時などの新しい環境に置かれた際にその環境ならではのルールや必要な知識を学び、適応していくべき場面で活かす事ができると思う。
そして今回の留学を通して得た最大の事は、様々な国や地域、さらには多様な知識や考え、文化背景をもつ人々と知り合えた事である。出会った他のAIMSの留学生や現地学生などは皆あらゆる事へそれぞれしっかりとした考え方をもっており、それぞれのやり方で自身の日々のこと(授業や課題)や将来のことに対して取り組んでいた。そのような様々な人々と知り合ってその考えや価値観に触れた事で、留学中だけでなく今後も互いに刺激し合いながら、それぞれで目標や夢に向かって前進していけると考える。これはUGMを留学先に選んで、現地で様々な友人を得た自分にしか得られなかったものだと思う。そのため、今回得た友人やその人たちから得た考え方を大切にして将来の目標に向かって邁進していきたい。
派遣先大学で特に良かった点
UGMは総合大学であるため、農学部以外の授業を受ける機会や派遣される農学部以外の他学部の学生と知り合いになれる機会が多いというのが良い点であると思う。
UGMは18学部、73学科から構成されており、授業や課外活動などを通して派遣中に多くの学部の友人を作ることができた。さらにUGMはインドネシアの中でも規模の大きい大学であるため、自分たちの他にも別のプログラムに参加している日本人留学生が多数いた。その留学生によって開かれたイベントの1つに日本語クラスがある。そのクラスに自分たちがUGMの学生に対する日本語教師として参加する機会があり、その教室を通して多くの生徒と知り合い、それらの生徒と休日を利用して遊びに行く事が何度かあった。インドネシアにはアニメなどの日本文化を通して日本語に興味をもち、日本語を積極的に学ぼうとする人たちが多い。そのため、すぐに多くの現地の学生と仲良くなれるのがUGMの魅力だと思う。
同じ大学へ行く後輩へのアドバイス
UGMは総合大学であるため、多様な文化や価値観に触れたい人におすすめの大学である。また、UGMの学生は留学生に興味をもって積極的に話しかけてきてくれる印象が強く、授業や課外活動に参加すれば様々な知り合いが必然的にできるといっても過言ではないと思う。私はその中で出会った現地の学生と更なるコミュニケーションを図るために、英語だけでなく現地語のインドネシア語の学習に励んだ。スマホアプリである“Duolingo”や持参したインドネシア語の本などで学んで、現地の友人と学習した言葉を使って会話したり、時には分からない言葉を質問したりすることもあった。すると彼らとの会話の幅が広がり、会話が盛り上がった。そのため、UGMで多くの友人を得たい人は留学前にインドネシア語を少しでも学んでおくことをおすすめする。また、留学に行って、現地で他学部と交流できる機会があったら是非参加してみてほしいと思う。想像以上に友達や物事の考え方の幅が広がると思う。