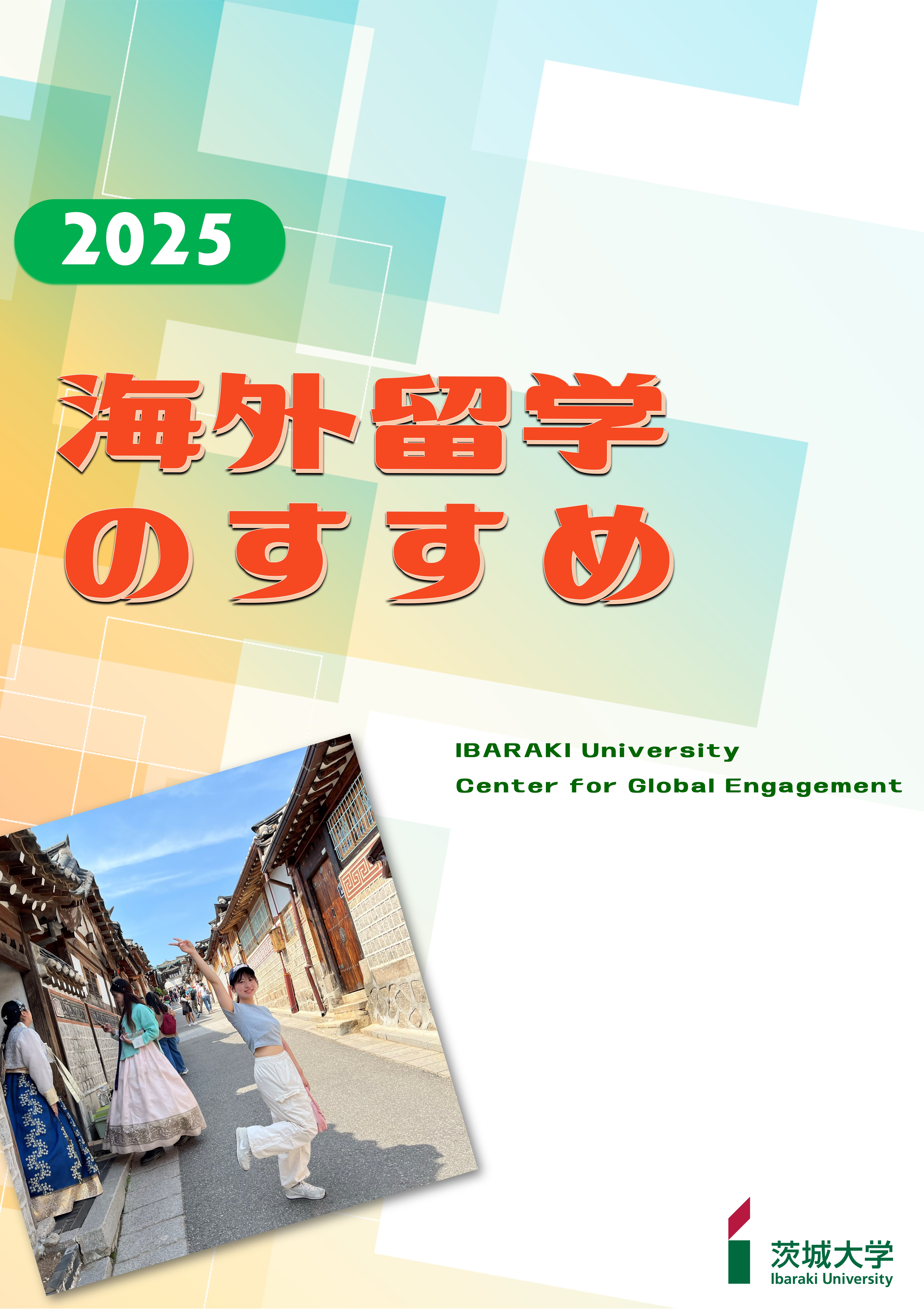海外留学を希望するみなさんへ
Introduction of Global Education Center
留学体験・協定校情報
インドネシアで見つけた日本人としての私

農学部
留学期間2024年度研修 AIMS派遣プログラム
授業で学んだ専門的な内容について
UGMで履修した科目は “Traditional Fermented Food of Indonesia”、“Plant Morphology and Systematics”、”Fishery Biology”、”Seed Technology”の4科目である。その内の“Plant Morphology and Systematics”と”Seed Technology”の2科目はPracticum(実習)クラスが含まれ、講義以外に実験や課外活動を含むPracticumの活動時間があった。これら4つの科目の中で特に印象的な科目は、“Traditional Fermented Food of Indonesia”と“Plant Morphology and Systematics”である。“Traditional Fermented Food of Indonesia”では、基本的にはインドネシアの発酵食品についての講義が行われ、講義内で学んだ発酵食品やその関連発酵食品についてのプレゼンテーションとディスカッションが行われた。授業内容はとても興味深いもので、初めてインドネシアの伝統的な発酵食品の材料や製造工程について学んだにもかかわらず、私たち留学生の出身国の発酵食品と比較しながら解説されたため理解しやすかった。
Fermented foodは、インドネシアはもちろん、世界の発酵食品について、化学的な視点から分析をして学び、セメスターごとに自分が調べた麴やインドネシアの伝統発酵食品であるTiwulについて、歴史や発酵過程などを踏まえてプレゼンを行った。
Plant morphologyは、植物形態や植物の分類学について学んだ。実習では、植物採集後にハーバリウムを作成したり、毎週植物のデッサンをして事細かに植物の細部を学んだりした。
Seed technologyでは、種子の生産、保管、流通などの種子にまつわることを学んだ。毎週の実験では、播種後のポットを観察して、APAスタイルでレポートを提出していた。
Annual cropでは、一年生作物の栽培方法や栽培環境について学んだ。インドネシア・韓国・ラオス・フィリピン・日本と同じアジアでも、栽培管理や栽培方法は全く異なることを、授業内のディスカッションを通して学んだ。また、実習では大学付近の農場でトウモロコシをいくつかのプロットを用意して栽培した。
海外の大学で授業を履修するにあたって工夫した点および反省点
工夫した点は、留学の4ヶ月前から、毎日英会話レッスンの受講し実践的な英語学習をして留学に備えた。また、挨拶程度のインドネシア語も本で学習をして、渡航した。
授業内では、紙ベースのノートをとって、手を動かし、分からないことや疑問などは、その授業内で積極的に、質問をしていた。またその日のうちに、学習した内容を振り返りノートにまとめていた。
分からない単語は、科目ごとに、マイ単語リストを作成してテスト前に見直した。
また分からないことは、WhatsAppなどで現地の学生や先生にすぐに質問して、その都度悩みをつぶしていった。
反省点は、インドネシア語の学習のプログラムがなく、インドネシア語を授業で学ぶ機会がなかったことである。また、AIMSの中に、practicum(実験)を、4つ以上受講して課題に追われている学生が多くいたため、多くても3つまでの取得がよいと考える。
多様な文化・価値観に触れることで得られたこと
インドネシアは80%以上がイスラム教を占めるイスラム大国である。そのため、普段の生活の中に、お祈りやハラル食品が身近にあった。食生活はもちろん、性格などにも国民性が表れていた。国によって異なり、インドネシア、韓国、ラオス、フィリピン、オーストラリアなど多国籍の方と関わる機会があった。実際に、私もヒジャブを身につけて、ハラル食品を取り、仲間と共にお祈りもした。
このように、現地での生活を通して文化や価値観に触れることで、多文化を尊重することはもちろん、自分たちの文化についても考えるきっかけになり、自分のアイデンティティを見直すことに繋がった。日本の文化については、生まれた時から接してきて、当たり前であるため、懐疑的に見ることはなかったが、インドネシアや他の国の文化に触れることで、改めて日本の文化や自分たちの価値観や考え方について考えるようになった。
留学で得た知識・経験を,自身の将来にどのように活かしていくか
私は今回の留学経験を以下のことに生かして、人生をあゆんでいく。
①奄美大島での農業インターンシップ
実際に、熱帯気候のインドネシアで学んだ農業形態を、生かしてインターンシップを行う。具体的には、蝸牛やパパイヤを用いた有機肥料の作り方である。自分が学んだことを日本でも実践し、それぞれの国の良さを取り入れていく。。
②国際的な視野を持って生きる
今までの交友関係は、国内の同じ年齢層が多かったが、留学を経て国籍や性別、年齢を超えて、様々な方と出会い、対話をさせて頂いた。今までにはなかった発想や考え方に出会い、自分とも向き合う機会になった。今後も様々な方との交流を重ねて、価値観を広げて人生に多くの選択肢を残していく。
③日本の文化をさらに学ぶ
インドネシアに行くことで、自分が日本人であり、日本の代表として接していくことが多かった。今後、国際的な仕事などをしていく際には、英語力も必要だが、それと同時に日本文化や歴史など、日本人として日本のことを学び伝えていく。
派遣先大学で特に良かった点
ガジャマダ大学は、総合大学のため、農学だけにとどまらず交流や学びを得たい方には、ぜひお勧め。また、イベントが毎週のようにある為、自分の勉強の進捗状況と照らし合わせて、参加することを強く勧める。更に、農学部の学生との交流だけではもったいないので、他学部はもちろん、インドネシアの方だけでなく、他の国から来ている留学生との交流も大切にしてほしい。
先生や先輩は、親切で優しいので、分からない事があれば、すぐにWhatsAppを用いて、どんな些細な疑問もすぐに解消することが大切。
インドネシア語の授業はないため、日本語クラスに参加してインドネシア語を学ぶか、独学で学ぶことを推奨する。(但し、授業は英語開講なので、インドネシア語習得は強制ではない。話せれば、なおよい。)