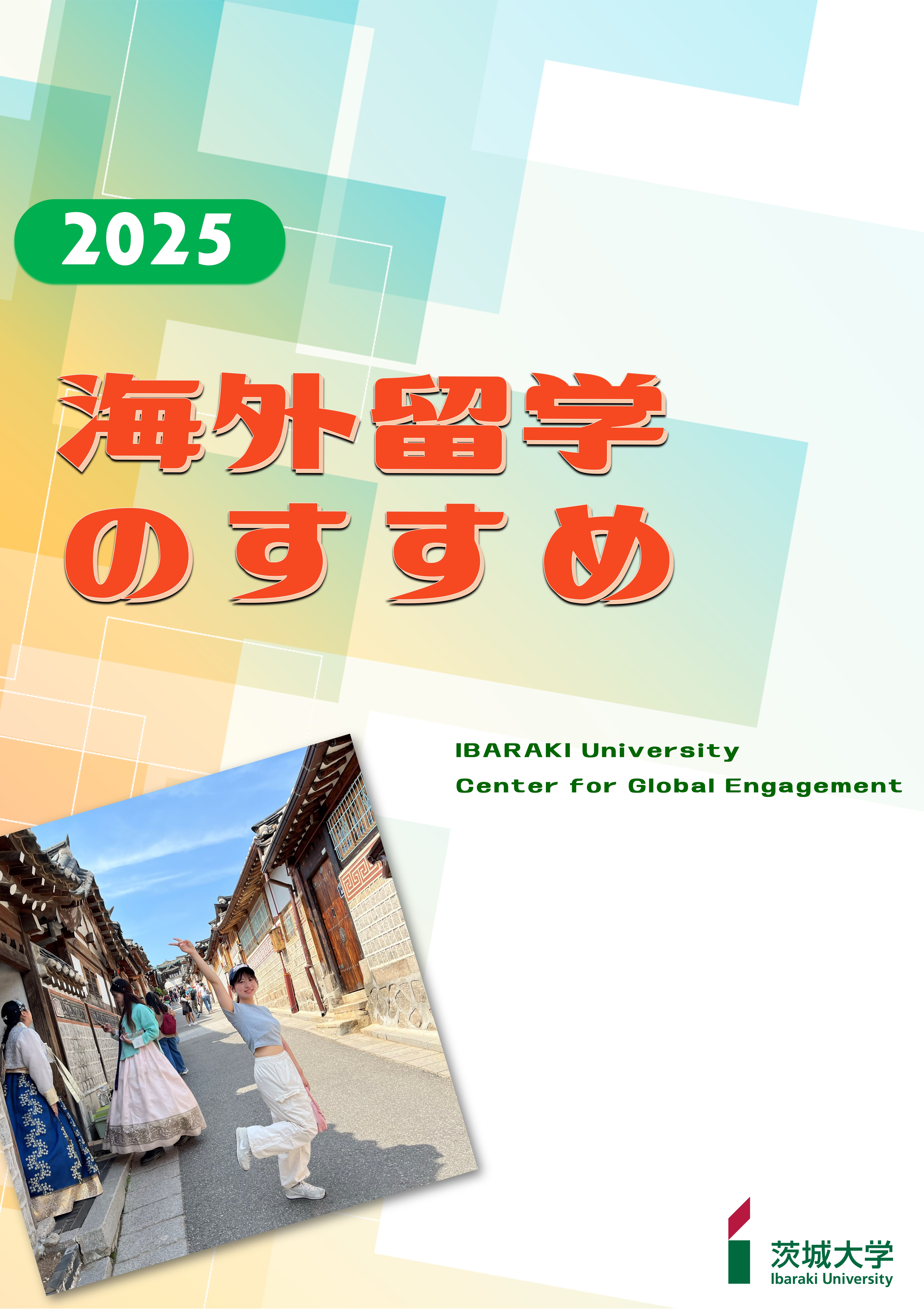海外留学を希望するみなさんへ
Introduction of Global Education Center
留学体験・協定校情報
タイで出会ったミャンマー人とイタリア人

農学部
留学期間2024年度研修 AIMS派遣プログラム
授業で学んだ専門的な内容について
GISの授業では、GISやリモートセンシングの原理、構造、それらがどのように環境研究に用いられているのかなど、環境科学ベースでGIS技術について学習した。週1回のラボではQGISなどのソフトウェアを用いて演習を行った。最後の授業では、GISデータを用いた土地利用に関するペアでのプレゼンを行った。一度日本で学んだ内容も多く含まれていたが、専門用語が多く英単語を覚えるのに苦労した。
Remediation Technologyの授業では、環境汚染物質の特徴やそれらの除去技術、除去に関する法律まで、環境修復に関することを幅広く学習した。この授業でも最後にプレゼンがあり、与えられた論文を読んで論文の背景から結論までを15分間にまとめて発表するというハードなものだった。さらに、論文を読んで解答する課題があったり、論文を基に作成されたテスト問題が出題されたりと、英語の論文に触れる機会が沢山あった。授業の大部分が初めて学ぶ内容であり、1回の授業に対する内容が非常に濃いため、理解に多くの時間を要した。
海外の大学で授業を履修するにあたって工夫した点および反省点
留学したての頃は、事前に授業資料のわからない単語を調べてから授業に臨むようにしていたため、授業内容を全て聞き取れなかったとしても概要をつかむことができた。しかし、授業資料が公開されるのが前日の夜や授業の直前であることが多く、授業に慣れてくると予習をしなくなってしまい、授業についていけなくなった。また、復習もあまりしていなかったため、テスト前に大量の資料を一から読むことになりとても大変だった。沢山時間はあったため、日々の復習を怠らなければよかったと思う。4年生のバディやクラスメートにテスト勉強の方法を聞いて勉強の方針を少し定めることができたのはよかった。また、私は日本では紙で授業を受けていたが、授業でスライドには書かれていない内容を大量に画面に書き込む先生もいたため、板書のスピードに追いつくためにタイでiPadを使って授業を受けたのは正解だった。
多様な文化・価値観に触れることで得られたこと
チェンマイ大学にはタイの学生はもちろん、ミャンマー出身の学生が多く在籍していた。私のクラスは約20人中6人がミャンマー出身の学生で、一度ミャンマーの大学に進学し、コロナウイルスやクーデターの影響でチェンマイ大学に入学し直したという学生も多くいた。国の情勢が安定せず、卒業後にやりたいことが自由にできるのかもわからない中、異国の地で真面目に勉学に励む同世代のミャンマー人学生たちの姿はとても刺激になり、定期テストに向けて何となく勉強していた今までの自分の学習態度を見直すきっかけとなった。また、ミャンマーに関して自ら調べるようになり、自分を気に掛けてくれる優しいミャンマーの学生たちの母国が安心して暮らせる状態にないということを知って心が痛むと共に、自分がいかに恵まれた環境で甘えて生きてきたのかを実感した。
留学で得た知識・経験を,自身の将来にどのように活かしていくか
派遣先大学で特に良かった点
チェンマイ大学には中心にある大きな図書館以外にも各学部棟に図書館があり、勉強する場所には困らなかった。また、大学内外に多くのカフェがあり、テスト期間も美味しいものを食べながら楽しく勉強できた。大学の正門側にはナーモー、裏門側にはランモーと呼ばれるエリアがあり、毎日多くの屋台や飲食店が並ぶため、徒歩移動で様々なものを食べることができた。学食もメインのフードセンター以外に学部ごとの食堂や寮ごとの食堂が利用できるなど充実していた。また、授業に関しては先生もクラスメートも親切で質問しやすく、わからないことを聞くと、思っていた以上に丁寧に答えてくれるため、わからなくて不安ということはほとんどなかった。私のクラスは少人数だったため、授業やプレゼンで極度に緊張することもなく、とても居心地がよかった。
同じ大学へ行く後輩へのアドバイス
私が留学した理学部には日本人学生がおらず、留学生自体も私とイタリアから来た学生の2人であった。そのため、授業に行けば英語でクラスメートと会話をする機会が必ずあり、とにかく英語を話したいという人にはおすすめである。他の学部から日本人留学生が理学部の授業を取りに来ることもあるため、常に日本人1人ということもなく、適度に英語と日本語を話せるという丁度良い環境だった。しかし、他の学部の授業を受講するのが難しいため、様々な分野の授業を受講したい場合には日本人学生が多く所属している人文学部に所属するのが良いと思う。また、住居に関しては、大学内の寮が満室であったため、自分で住む場所を探す必要があった。初めは理学部の担当者に勧められた、数年前に茨大の先輩方が住んでいた家賃が安め(約4500thb)のアパートに住んでいたが、合わなかったため1カ月で他のアパート(約6300thb)に引っ越した。事前にアパートの環境や設備をよく確認してから決めた方が良いと思う。